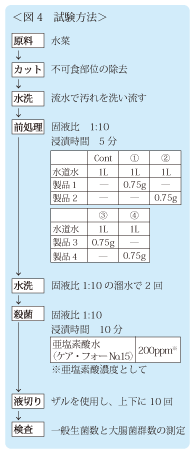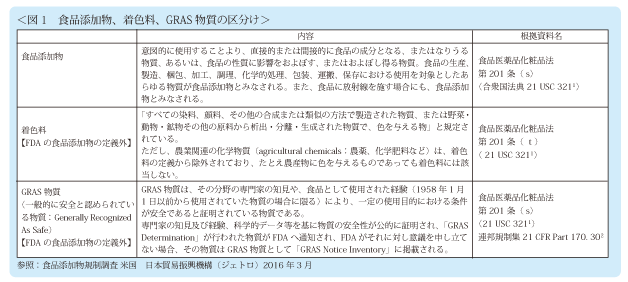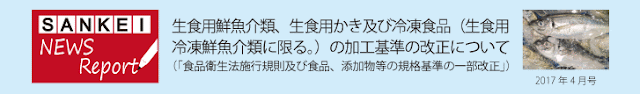
近年、生食用鮮魚介類の加工基準の改正が進んでいますが、この加工基準は、「食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について」という厚生労働省告示によって法制化されており、その始まりは昭和46年と意外に古く、その当時は鮮魚介類には化学合成品たる添加物はいかなる理由があっても使用してはならないと定めていましたが、近年の食品の多様性を考慮し、殺菌を目的とする場合に限り、その安全性が確認出来た食品添加物については加工基準の中に取り入れていくという方向性が生まれ、平成13年からは殺菌を目的とした場合に限り、次亜塩素酸ナトリウムが生食用鮮魚介類に使用することができるようになり、これによって衛生基準を満たすことができるようになりました。
さらに平成28年には2回改正され、生食用鮮魚介類への直接殺菌剤として、亜塩素酸水、次亜塩素酸水などの新しい殺菌技術が追加されました。<表1>
加工基準における原料用鮮魚介類に対する添加物の使用について
生食用鮮魚介類の加工基準の中には、“原料用鮮魚介類”という表現があり、平成13年厚生労働省告示第213号において、「第213号における生食用鮮魚介類の加工基準中の(5)の処理を行っていない鮮魚介類については、化学的合成品たる添加物の使用規定は適用されないこと。」という記述があります。
またこれは、生食用鮮魚介類として加工される以前の鮮魚介類については、化学合成品たる添加物の使用を妨げるものではないという事でもあり、原料用鮮魚介類の段階では、衛生基準を満たすため、いわゆる殺菌を目的としている場合、化学合成品たる添加物を使用できるという事になります。
但し、食品添加物の使用基準と、最終製品において、消費者誤認を招くような欺瞞的使用方法は、添加物本来の目的とは異なる為、認められていないことは大前提となります。
生食用鮮魚介類を原料にした場合の加工基準
生食用鮮魚介類は、原料用鮮魚介類に殺菌処理を施すことによって衛生的な状態となった最終製品であり、生食用鮮魚介類を原料として購入し、再度、生食用鮮魚介類に加工した場合、その取り扱いには十分な注意が必要となります。
特に、海外でフィレ加工した生食用鮮魚介類を原料として輸入し、これを国内で生食用鮮魚介類として再加工した場合、原料用鮮魚介類とは認められず、この原料は生食用鮮魚介類の加工基準が適用済みの状態となり、化学合成品たる添加物を使用することはできません。<表2>
これは、そもそも生食用鮮魚介類に加工された段階で、すでに衛生基準が満たされているはずであるという考えが根底にあるからです。
生食用鮮魚介類とその対象業者
最終製品として市場流通される生食用鮮魚介類は、一般に消費者が加熱せず、そのまま摂取する事が前提であり、軽度な加工が施されるもの(刺身、すし、和え物、酢の物)だけはこの中に含まれています。また、対象業者としましては、魚介類せり売業者、仲買業者、魚介類販売業者、製造加工業者、 および一部の飲食店営業者であり、製造加工業者としては、むき身業者、ゆで貝、 ゆでたこ、ゆでいか、ゆでかに、ゆでえび等の製造加工業者、生節の製造業者、生しらすの製造業者と、一部の飲食店営業者であり、この一部の飲食店営業者には、すし屋及び刺身等を作る料理店が含まれていますので、やはり最終製品となる生食用鮮魚介類を消費者へ提供する業者が対象であるということはわかっていただけるのではないでしょうか?
また、冷凍食品(生食用鮮魚介類に限る。)及び生食用かき(生食用鮮魚介類等)についても生食用鮮魚介類と同様に改正されており、<表3>このように、生食される鮮魚介類については、全体的に改正され、最終消費者に対する食の安全性を確保する為に、衛生基準を担保するという点が、より強調された結果だと言えるのではないでしょうか?

まとめ
これまで、漁港に併設されていた加工場では処理水に海水を直接使用していましたが、この海水を殺菌し、飲用適の食品製造用水を用いることにした平成13年の加工基準大幅改正により、これ以降、腸炎ビブリオによる食中毒は激減することとなり、これは国内企業の衛生管理基準の強化による賜物であると捉えられています。
しかし、海外で加工されたものも生食用鮮魚介類であり、これを国内で二次加工して生食用鮮魚介類として商品化する際には、すでに加工基準が適用済みであることをご存知ではない方も多く、今や、コンビニでも寿司が販売されている時代であります。今回、改正されました食品衛生法につきましては、再確認していただきますと共に、安全な鮮魚介類が正しく流通されることを望んでやみません。
SANKEI NEWS Report 4月号 PDF版↓
https://drive.google.com/open?id=0BwbDyV31W2pXLVIyd29jVU5ZNTA
SANKEI NEWS Report 4月号 PDF版↓
https://drive.google.com/open?id=0BwbDyV31W2pXLVIyd29jVU5ZNTA